- 引っ越し時にバイクを輸送する方法
- バイクの輸送費の相場価格
- 引っ越しでバイクを輸送する際の注意点
- 引っ越しに伴うバイクに関する手続き
バイクに乗っている人が引っ越す場合、バイクも一緒に持っていく必要があります。近距離の引っ越しならば、自分で運転すれば問題ありませんが、長距離の引越しだと、バイク輸送を依頼することになります。
この記事では引っ越しの際にバイクを輸送する方法と料金相場、バイクを運ぶ際の注意点についてまとめています。
現在、バイクを所有していて引っ越す予定がある人は、ぜひ参考にしてください。
安い引っ越し業者が見つかる一括見積もり査定サイト
引っ越し費用をできるだけ安くしたい場合は、引っ越し業者の一括見積もりサイトを利用するのがおすすめです。複数業者の見積もりをとることで、引越し費用の相場や格安で引っ越しをしてくれる業者を見つけることができます。
おすすめ一括見積もりサイト:引越し侍

提携する引っ越し業者が370社以上と、ほかのサイトと比較しても圧倒的に多い一括見積もりサイトです。大手の引っ越し業者だけではなく、地域密着型の中堅・小規模業者とも数多く提携しています。引越し侍ユーザーによる口コミも多数掲載されているため、利用した人の本音をチェックすることができます。
引っ越し時にバイクを輸送する方法
引越し時にバイクを輸送する主な方法は、以下の3つです。
- 自分で運搬する
- 引っ越し業者に依頼する
- 専門の輸送業者に依頼する
バイクを輸送する方法①自分で運搬する
もっとも手軽な方法は、自分でバイクに乗って運搬することです。
費用などがかからないため、できるだけ引越し費用を抑えたい人におすすめです。ただし、短距離の移動ならば問題ありませんが、長距離移動は肉体的にも負担がかかります。また、引越し当日は荷解きなどで忙しいことが多く、移動時間がもったいないというデメリットもあります。
また、トラックやミニバンなどにバイクを積んで自分で運搬する方法もあります。この場合、輸送中にバイクが倒れて破損することもあるため、運搬に注意が必要です。
バイクを輸送する方法②引っ越し業者に依頼する
引越し業者では、オプションとしてバイクの陸送を行っていることがあります。
家財とまとめて依頼できるため、余計な手間がかかりません。引越しプランによっては、専門業者よりも安くバイクを運搬できることも多いです。
ただし、すべての引越し業者がバイクを運んでくれるとは限りません。また、一般的な引っ越し業者は車両運送は専門業者に委託するため、料金が割高になることが多いです。
バイクを輸送する方法③専門の輸送業者に依頼する
引っ越し業者ではなく、バイク輸送の専門業者に依頼する方法もあります。
専門業者と直接契約することになるため、引っ越し業者からの委託よりも手数料がかからず、安いことが多いです。専門業者のバイク輸送の金額は、引っ越し業者よりも10~20%ほど安いことが多いです。
バイク輸送の専門業者は複数あり、それぞれ料金体系が異なるため、複数業者の見積もりをとって、どこが1番安いか調べてみましょう。
バイク輸送費の相場(50cc・250ccの場合)
実際にバイクを輸送する場合、どのくらいの料金になるのか相場をまとめてみました。
50ccのミニバイク・原付バイクの輸送費の相場
東京から50ccのミニバイクを輸送する際の料金は、だいたい以下の通りです。
| 東京から北海道 | 48,000円 |
| 東京から福島 | 25,000円 |
| 東京から静岡 | 20,000円 |
| 東京から鳥取 | 27,000円 |
| 東京から福岡 | 25,000円 |
東京から本州だとだいたい20,000円程度の輸送費が相場です。北海道は船便などを利用することになるため、輸送費が高くなってしまいます。
250ccのバイクの輸送費の相場
東京から250ccのバイクを専門業者に依頼したときにかかる料金の相場です。
| 東京から北海道 | 50,000円 |
| 東京から福島 | 26,000円 |
| 東京から静岡 | 21,000円 |
| 東京から鳥取 | 29,000円 |
| 東京から福岡 | 26,000円 |
50ccのミニバイクと比較して、250ccはそこまで料金に違いはなく、だいたい1,000円ほど料金がアップする傾向にあります。場合によってはバイク輸送の専門業者よりも、引っ越し業者に依頼したほうが費用が安くなることがあるので、必ず複数業者の見積もりをとるようにしましょう。
引っ越しでバイクを輸送するときの注意点
引っ越しでバイクを輸送する際は、以下の点について気をつけましょう。
- ガソリンを抜いておく
- キズや破損状況を確認しておく
バイク輸送の注意点①ガソリンを抜いておく
自分でバイクを運転していくのではない限り、バイクのガソリンは事前に抜いておきましょう。ガソリンが残っていると、輸送中に引火する恐れがあるため、注意が必要です。
また、業者に依頼する場合も、バイクにガソリンが入ったままだと輸送を引き受けてくれない可能性があります。ガソリンはとても引火しやすく、抜いた後の保存にも注意が必要のため、自分で抜くのが心配な場合はディーラーなどに抜いてもらうのがおすすめです。
バイク輸送の専門業者だと、ガソリンを業者が抜いてくれることもあります。二度手間にならないように、事前にガソリンを抜く必要があるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
バイク輸送の注意点②キズや破損状況を確認しておく
バイク輸送中にキズや破損してしまう可能性があります。キズがついたのがどのタイミングかわからないと、賠償を受けられない可能性が高いです。
いつバイクにキズがついたのかを証明するためには、バイクを輸送する事前に状況を記録しておく必要があります。輸送前のバイクがどのような状態だったのかわかるように、輸送を依頼する前に写真を撮っておきましょう。
バイクが破損した場合の補償は、業者によって違いがあります。万が一の時、どういった対応をしてもらえるのかは事前に確認しておきましょう。
バイク輸送に対応している引っ越し業者
オプションなどでバイク輸送に対応している引っ越し業者をまとめました。
| ヤマトホームコンビニエンス | 大型バイクの輸送にも対応。 バイク輸送は専門業者に委託。 |
|---|---|
| 日通(日本通運) | すべての車種のバイクに対応。 バイク輸送は専門業者に委託。 |
| アート引越センター | バイクはほかの家財と別に運搬。 |
| アーク引越センター | 50ccまでの原付バイクは、引っ越しプラン内の料金で運搬可能。50ccを上回る場合はオプションサービスで対応。 |
| アリさんマークの引越社 | 有料のオプションサービスで対応。 |
| サカイ引越センター | 車両輸送として提携輸送業者に委託。 |
引っ越し業者に依頼すれば、ほかの家財の運搬と窓口を一本化できるので、手間がかかりません。
バイクの輸送は、排気量、大きさによって運搬方法や料金が変わってきます。引っ越し業者にバイク輸送を頼む場合は、見積もりの段階でバイクの排気量などを必ず伝えるようにしましょう。
50cc以下の原付バイクだと、ほかの荷物と同じように運搬してくれる業者もいます。この場合、燃料タンクにガソリンが入っていると危険物扱いになるため、運んでもらえません。そのため、引っ越し業者にバイク運送を依頼する場合は、必ず事前にガソリンを抜いておく必要があります。
自分で手動ポンプを使ってガソリンを抜くこともできますが、ちょっとした静電気などでも引火する恐れがあるため、バイクショップなどに依頼したほうが安全です。
引っ越しに伴うバイクの住所変更の手続き
引っ越しによって住所が変わった場合、バイクの住所変更も行わなければなりません。
手続きに必要な書類はバイクの排気量によって異なります。
125cc以下のバイクの手続きに必要な書類
125cc以下の原付自転車の場合に必要な書類は以下の通りです。
- 廃車申告受付書(廃車をしていない場合は標識交付証明書と前登録地のナンバープレート)
- 印鑑
- 届出人本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 委任状(提出するのが本人でない場合)
125cc以下のバイクが同じ市区町村内で引っ越しをする場合、転居届を出すことで住所が変更されるので、手続きの必要はありません。
126cc~250cc以下のバイクの手続きに必要な書類
126〜250cc以下(軽二輪自動車)の場合に必要な書類は以下の通りです。
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証記入申請書
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 住民票(3カ月以内のもの、写しで可)
- 印鑑
- 委任状(提出するのが本人でない場合)
- ナンバープレート(引越し先が以前とは違う運輸局の管轄になる場合)
軽二輪自動車には車検がないため、軽自動車届出済証が必要になります。紛失時には再交付を申請し、ナンバープレートが返納できない場合は、警察への届出や理由書の提出が必要になります。
251cc以上のバイクの手続きに必要な書類
251cc以上の小型二輪自動車の場合に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書
- 住民票(3カ月以内のもの、写しで可)
- 印鑑
- 委任状(提出するのが本人でない場合)
- ナンバープレート(引越し先が以前とは違う運輸局の管轄になる場合)
忙しい場合は代行業者に依頼
引っ越しに伴うバイクの手続きは、必要書類が多く、記載事項も複雑なため、どうしても時間がかかってしまいます。慣れないことも多く、しかも手続きには15日以内というタイムリミットもあるため、自信がない場合は、代行業者に依頼するのがおすすめです。
代行業者に依頼することで、全国どこからでも手続きしてもらうことができます。受付窓口の営業時間にもしばられないので、なかなか時間がとれない人でも手続きを完了させることができます。
ネットでの手続きと書類の送付だけで作業が完了するので、引っ越しでなかなか時間がとれない場合は代行業者への依頼を検討してみましょう。
引っ越したのにバイクの住所変更を行わないことで起こるトラブル
バイクの住所変更は、引越し後15日以内に手続きをする必要があります。
では、引っ越したにもかかわらず、バイクの住所変更を行わないと、どういったトラブルが起こり得るのでしょうか。
- 納付書が届かない
- リコールの通知が届かない
バイクの住所変更のトラブル①納付書が届かない
引越し後にバイクの住所変更を怠ると、自動車税や軽自動車税の納付書が届かない可能性があります。
納税書が届かなかった結果、納税を忘れてしまうと延滞金が発生する恐れがあります。また、車検がある小型二輪車では納税証明書が必要で、これがないと車検が受けられません。
こうしたトラブルが起こりうるため、必ず引っ越した際はバイクの住所変更を行うようにしましょう。
バイクの住所変更のトラブル②リコールの通知が届かない
バイクの住所変更を行わないと、リコール通知が届かない恐れがあります。
リコールは車両の安全性に関わる重要な情報です。リコール通知が届かないと、必要な整備が受けられず、故障や事故のリスクが高まります。
リコールに速やかに対応するためにも、必ず引越し後にバイクの住所変更手続きを行いましょう。
バイクの引っ越しについてのよくある質問
バイクの引っ越しについてよくある質問とその答えをまとめました。
- 引っ越しでバイクを運搬した場合、住所変更の手続きはいつまでにする?
- バイクの住所変更の手続きを忘れていた場合、どうすればいい?
- 引っ越した場合、原付バイクの手続きはどこで行う?
- 引っ越しでバイクを運搬した場合、住所変更の手続きはいつまでにする?
-
原付などのバイクの住所変更は、引越し後15日以内に手続きをすることが道路運送車両法で定められています。15日間を過ぎてしまうと、法律により最大50万円の罰金が科される恐れがあります。
- バイクの住所変更の手続きを忘れていた場合、どうすればいい?
-
速やかに対応するようにしましょう。原付の引っ越しで、廃車手続きを先に行ってしまうと運転できなくなってしまいます。そのため、引越し先で手続きをするのがおすすめです。住所変更の手続きをしないと公道を走れなくなるため、忘れずに手続きしておきましょう。
- 引っ越した場合、原付バイクの手続きはどこで行う?
-
原付バイクの手続きは各市区町村の役所で行います。旧住所の役所で廃車届を提出し、新住所の役所で新しく登録手続きが必要になります。旧住所での手続きを忘れないようにしましょう。
バイクの引っ越しについてのまとめ
バイクの引っ越しについてまとめました。
- 自分で運搬する
- 引っ越し業者に依頼する
- 専門の輸送業者に依頼する
- ミニバイク・原付バイクの輸送費の相場はだいたい20,000円
- 250ccのバイクの輸送費の相場は原付よりも1,000円程度高い
- バイクのガソリンを抜いておく
- キズや破損状況を事前に確認しておく
バイクの引っ越しで気をつけたいのは、排気量によって手続きの受付窓口と必要書類が異なるという点です。もし手続きが面倒な場合は、代行業者に依頼するという方法もあります。
引っ越しの際のバイクの輸送は、引っ越し業者に依頼したり、専門業者に依頼したり、自分で運んだりすることができますが、やはり専門業者に任せるのが確実で安心できます。自分で運ぶ場合、故障やキズがつく恐れがあるため、くれぐれも気をつけて運搬するようにしましょう。
また、運転免許証は身分証明書として使うことが多いため、引越し後はなるべく早く住所変更の手続きを済ませておきましょう。
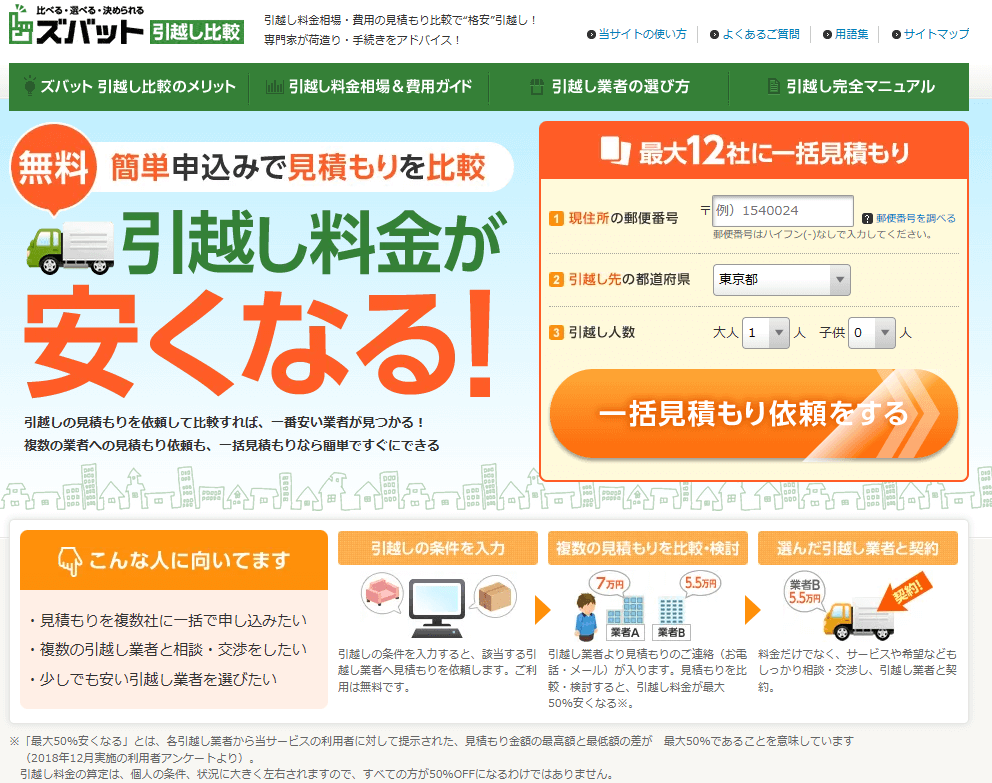

コメント